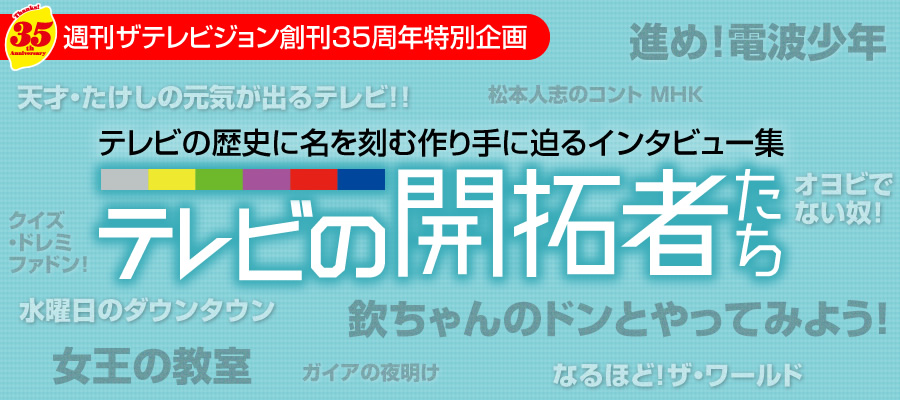「石橋さんが本番前に面白いことを話し始めたら、慌てて止めています(笑)」【「石橋貴明のたいむとんねる」プロデューサー / 関卓也】
とんねるずの笑いとは、その場の瞬発力で生まれるものなんです

――バラエティー部への異動は、自らの希望で?
「いえ、これもまた突然の異動でした。今にして思うと、きっかけとなったのは、ジョビジョバ主演のコメディードラマ『魔がサスペンス劇場』(2000年フジテレビ系)かなと。あの番組をやっていたとき、当時ドラマ部の上司だった大多亮さんから、『関は、バラエティーの方が合ってるかもな』とよく言われたんですよ。そのときは冗談で言ってるのかな、なんて思ってましたけど、ちゃんと考えてくれてたんですよね。そこで、最初に携わったのが『みなさんのおかげでした』だったんです」
――とんねるずのお二人との番組作りは、どのようなものだったんでしょうか。
「僕はもともとモンティ・パイソンが大好きで、ああいう、作り込んだコメディーをやってみたいなと思っていたんですね。ところが、とんねるずの笑いはそれとは全く違っていました。まず何より、石橋(貴明)さんも憲武さんも、お二人とも予定調和を嫌う。例えば、カメリハで、雑談をしながらスタッフを笑わせることがよくあるんですが、リハーサル中にスタッフにウケた話は本番では一切しないんです。お二人にとって笑いとは、その場の瞬発力で生まれるもの。『新鮮なものでなければ、テレビの向こう側には届かない』という考えが基本にあるんだと思います。そして実際、その方が抜群に面白い。とんねるずの笑いというのは、僕なんかがどんなに一生懸命笑いを作り込んだところで、まるで追い付かないすごさがあるんですよね」
――では関さんにとって、ターニングポイントになったお仕事は?
「人との出会いという意味では、一番大きいのはやはり、とんねるずのお二人との出会い。これは間違いないです。
個々の仕事で言うと、ドラマ部に行ったときが一つの転機でしたね。それ以前、スポーツ番組を作っていた時代は、いわばドキュメンタリーを作っていたと思うんですよ。番組を作るということは即ち、アスリートたちの、ありのままの姿を追うことだった。出来上がったものは、ナレーションを入れて、かっこよくカットをつなぎ、一つのストーリーとしてまとめられてはいるけれど、現場では、カメラを向ける相手に対して、何かをしてくださいと指示することはありません。せいぜい、『陸上のトラックをここからあそこまでかっこよく歩いてくれますか』とお願いするくらい。『こういう気持ちで歩いてください』なんて演出はしないんですね。ところが、これがドラマになると、カメラを向ける対象を、心情の部分から演出しなくてはならない。そこをちゃんとやらないと、演者さんは動いてくれないんですよ。ドラマに携わって、演出とはこういうことなんだと改めて気付かされました。これはかなりの衝撃でした」
――演出する上で、ドキュメンタリーとフィクションは全く違うんですね。
「昔から映画が好きだったこともあって、カット割だとか画角だとか、そういったことには思いが至るんですけど、ドラマの現場に行って、人間の演出という新たな壁にぶつかってしまったというか。『美少女H』を作っているときに、中江功さんがディレクターとして参加していて、いろんなことを教えてくれたんですよ。『カット割はカメラマンが考えてくれるから、ディレクターは“人”を演出しないとダメなんだ』とか、パソコンを見ながらボソボソと低い声で(笑)。そうやって、ドラマの“いろは”がようやく分かってきたところで、バラエティー部に異動になっちゃったんですけどね」