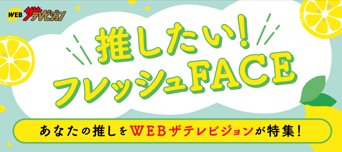NNNドキュメント’25の放送内容一覧
香川の地で40年近く続いてきた“アマチュア”合唱団の「かがわ第九」。ベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」を、職業、年齢、価値観、何もかも違う100人が声を一つにして歌い上げる。合唱団をけん引してきた実行委員長の急死、資金難、団員の高齢化など問題が浮き彫りになる中、なぜ歌うのかという意味を問う。
2015年、青森中央高校演劇部は青森空襲体験者への取材を基に舞台「7月28日を知っていますか?」を作り上げた。以来、空襲の日に上演を重ねて記憶をつなぐも、2025年は全国大会と重なり上演ができなくなる。そこで演劇部のOB・OG14人が立ち上がる。再び体験者の声に耳を傾け、彼らが伝えるメッセージに迫る。
戦時中、広島の路面電車の運行を支えたのは15歳前後の女学生だった。彼女らは被爆の3日後に電車を復旧させ、焼け野原になった街に電車を走らせた。しかし終戦後、担い手が戻ると、その任務を解かれた。あれから80年、数少なくなった元女学生を捜して取材を敢行。戦争に踊らされた“幻の女学生”の人生をたどる。
現役教員による児童の盗撮画像を共有するグループの存在。本来は子供を守るべき教員という立場を利用した卑劣な犯行はなぜ起きたのか。児童や生徒を「性の対象」と見る異様さ、SNSには未成年を狙った悪質なコミュニティーの存在が拡大している。子供の安全を守るため社会に突き付けられている課題に迫る。
昨年全国で亡くなった一人暮らしの人は約7万6000人。鹿児島市に住む男性は、国家試験の合格を目指しながらその失敗をきっかけに人生が暗転。わが子と断絶し、亡くなった。孤独死は他人事ではなくボタンの掛け違いで誰しも可能性がある。常に死と向き合う特殊清掃会社の男性の目を通して、「生」について考える。
太平洋戦争末期、熊本から出撃した特攻作戦の任務に当たった「義烈空挺隊」。米軍に占領された沖縄に強行着陸し、敵機や施設を破壊する過酷な任務で113人が戦死した。一方、県内には隊員が通っていた元銭湯が存在し、当時の女性主人は慰霊のために菩薩像を建立した。義烈空挺隊の実像をひもとく。
骨や関節の正常な発育が妨げられる「アペール症」は15万人に1人の難病で、手足の指がくっついて生まれてくることが多いため、複数回の手術が必要となる。福岡市に住む12歳の少女の指は他人よりも小さく関節は曲がらない。2025年の春、彼女が小学校卒業の集大成としてピアノのソロコンサートに挑戦する姿を追う。
大阪・関西万博の会場に立ち並ぶ158の国と地域のパビリオン。先進国イタリアのパビリオンには“国宝級”の芸術作品が並ぶ一方、世界最貧国とされるブルンジは大阪のベーカリーを巻き込み、自分の国を知ってほしいと奔走する。開催期間わずか184日の万博は私たちに何を発信し、未来に何を残すのかを見つめる。
終戦から2週間後、捕虜に物資を運んでいたアメリカの爆撃機B29が秋田の山に墜落した。生存兵を「殺害しろ」という声も上がる中、麓の住民に助け出され、無事帰国した生存兵は、その後秋田を再訪し感謝を伝えた。山中に残されたB29の一部や取材を基に、生存兵と救出した住民が紡ぎ出した“今”に光を当てる。
特攻隊員の遺品などを展示してきた予科練資料館は、特攻隊員だった一人の男性が1988年に大分市の自宅に開設された。平和の大切さを訴えてきた男性は2021年に亡くなり、長男が管理を引き継ぐも担い手がいないことから閉館となった。その後、戦没者をまつる神社へと移され、戦争の記憶を伝えている所蔵品に迫る。
「イカ王子」を名乗り、三陸の海の幸を全国にPRしてきた、岩手・宮古市に住む一人の男性に迫る。代表取締役専務を務めていた水産加工会社がイカの不漁などで経営破綻。崖っぷちに立つが今年復活を宣言し、活動を再開した。「水産のエース」と呼ばれた彼の生きざまと世界三大漁場・三陸が抱える課題を見つめる。
心臓病の子供は、成長に合わせて何度も過酷な手術を受けなければならない。そんな手術を1回でも減らすため、日々新たな医療機器の開発に取り組む小児心臓血管外科医の男性に迫る。欧米諸国に遅れをとる日本の医療機器開発だが、自身もわが子を亡くした身である男性が歩み続ける姿や言葉から、希望を見いだす。
障がいのあるなしに関わらず、みんなで一緒にさまざまなことを学ぶ「インクルーシブ教育」。福井・福井市の公立小学校に入学した医療的ケア児の少女と、クラスメートたちの1年にカメラが密着。子供たちは、自分とは異なる個性や価値観を受け入れてきた。インクルーシブ教育を通して、共生社会を考る。
戦闘機で敵艦に体当たりする特攻の際、元軍医の男性が上官から命じられたのは、出撃前の特攻兵に注射を打つことだった。戦後、その注射が覚醒剤“ヒロポン”だと知り、がくぜんとしたという。男性は今年3月に亡くなり、「露の世に残す不戦の志」と俳句で“不戦”を訴えていた。男性の生涯消えなかった後悔に迫る。
1985年8月12日、日本航空123便が群馬・御巣鷹の尾根に墜落し520人の命が失われた。現場からは、乗客らが家族と引き裂かれる直前に残した遺書が見つかり、それは墜落までのわずかな時間で懸命につづられた“最期のメッセージ”だった。事故から40年、遺書と共にその後の人生を歩んできた遺族たちの“今”に密着する。