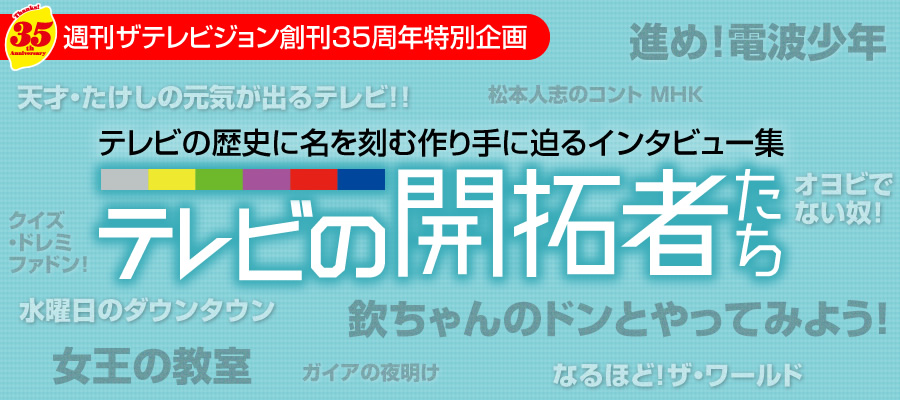【テレビの開拓者たち / 野島伸司】「後世まで語られるような質の高い作品を残していきたい」
1988年に「時には母のない子のように」でフジテレビヤングシナリオ大賞を受賞し、同年「君が嘘をついた」(フジ系)で連続ドラマの脚本を初めて担当。その後、「101回目のプロポーズ」(1991年)、「愛という名のもとに」(1992年)、「ひとつ屋根の下」(1993年)など、フジ系のトレンディドラマを多数手掛ける一方、後に“TBS野島三部作”と呼ばれる「高校教師」(1993年)、「人間・失格~たとえばぼくが死んだら」(1994年)、「未成年」(1995年)など、今の地上波では放送が困難と思われる衝撃作を世に送り出し、多くの視聴者を釘づけにしてきた脚本家・野島伸司氏。この秋、野島作品初のHuluオリジナル連続ドラマとなる「雨が降ると君は優しい」で、“セックス依存症”という新たなテーマに挑戦する彼に、脚本を書く上での心構えやポリシーを改めて語ってもらうとともに、昨今の“テレビの規制”の問題についても意見を聞いた。
物語の中に“枷(かせ)”を作る。そこに最も腐心しています

──野島さんと言えば、“TBS野島三部作”に代表されるように、センセーショナルな内容で人間の暗部を描く作家、という印象を持っている人も多いと思うのですが、実際は、ホームドラマや純愛ものなど、いろんなジャンルの作品を手掛けてらっしゃいますよね。
「僕の中には何人か種類の違う物書きがいるんですよ。だからコメディーとか、ライトタッチの作品を書くのも大好きなんですけど(笑)。ただ、自分の名前が世に知られるようになったきっかけが、TBSの一連のディープな作品だったというだけで」
――そうしたさまざまなテイストの作品を手掛ける中で、全ての作品に通底しているものは?
「僕としては、どんな作品でも、人間のピュアな部分、人間の本質を描きたいと思っています。そのために、物語の中に何か一つ“枷(かせ)”を作ることを心掛けているんです。例えば、『高校教師』では、繭(桜井幸子)は父親との関係において、ある重大な秘密を抱えていましたが、あれは繭と教師の隆夫(真田広之)の関係をよりピュアなものへと昇華させるための枷であって、決して物語の主旋律ではないし、ましてや、センセーショナルなものを狙っているわけではない。きれいな小川の流れを見せたいときに、その横に大きなドブがあると川の美しさがより強調されるというか(笑)、大きな枷が一つあることで、物語や登場人物のピュアな部分が明確に浮き上がってくるんです。特にラブストーリーを作るときは、主人公の男女に、どんな枷を与えるのか。そこを発明するのに最も腐心しています」
──逆に「こういう作品は書きたくない」といったポリシーはありますか?
「人品が卑しい人間は書けない、ということです。脚本家というのは、ストイックにならなきゃいけない局面がすごく多くて。例えば、“浮気はダメ”という話を書いたとする。そうしたら僕も絶対に浮気しちゃダメだと思うんですよ。そうやって自分の作品に責任を持たないと、書いたものが“言霊”にまでなれないというか、他人に伝わっていかないと思うから。で、そんなことを日々考えているうちに、必然的に家にこもりがちな生活になってしまう(笑)。世間では、僕が派手な暮らしをしていると思っている人もいるかもしれませんけど、実はかなりの引きこもりなんです。まぁ、脚本家になる前からそうなんですけどね(笑)」