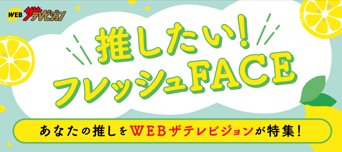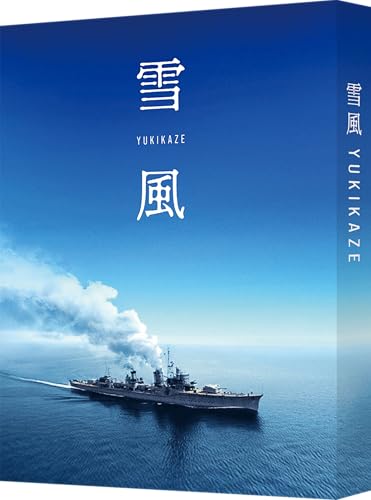静かに、しかし確実に話題を集めるアニメ映画「ホウセンカ」。いまなお根強い人気を誇るアニメ「オッドタクシー」を手掛けた木下麦×此元和津也タッグが新たに臨んだ新作アニメ映画で、10月10日の公開からエンタメ色が強い現在の流行とは一線を画す特徴的な演出が注目を呼んでいる。派手なアクションも過剰な説明もない物語の中でいったいなにが見る者の心を動かし、深い感動へと誘うのか。その芯に迫る。
令和のいま作られた「時間が証明する感情」
映画「ホウセンカ」は、無期懲役囚の老人・阿久津が主人公。独房で病に伏し、孤独な死を迎えようとしていたヤクザに、突如として人の言葉を操る一株のホウセンカが語りかけた。この不思議な“会話”をきっかけに、阿久津は自身の過去を振り返り始める。
1987年…若きヤクザとして愛のために命をかけて奔走した日々。物語はヤクザの汚れた稼業とバブル崩壊に伴う衰退、吹き溜まりのような人生のなかで唯一揺るがなかった「愛」という相反するテーマを静かに問いかけるのだ。
先述したとおりアニメ「オッドタクシー」の木下麦と此元和津也が再びタッグを組んだ同作。前作で示された「会話劇の妙」「張り巡らされた伏線」「予測不能な人間ドラマ」といった魅力はそのままに、「ホウセンカ」ではより挑戦的な“逆行”が見え隠れする。
「ホウセンカ」の舞台は独房という閉鎖空間と阿久津の回想する過去の日常に限定されており、演出はさらに抑制的だ。この演出はアニメという表現手段の持つ過剰な表現力とエンタメ感を意図的に削ぎ落とし、いわゆる実写作品のような奥行きとリアリティーを生む。
主要CVキャストには老境の阿久津を演じるベテラン俳優・小林薫に“過去の阿久津”を演じる戸塚純貴、人の言葉を話すホウセンカを演じるピエール瀧という異色の顔ぶれが並んだ。小林の演技はアニメ特有のわかりやすく濃淡が濃い表現とは違い、至って自然な会話のトーンを維持する。またピエール瀧は「しゃべる花」ホウセンカという不思議なキャラクターを担当。阿久津の人生を容赦なく、時にユーモラスに問い詰めていく難役を見事こなした。
制作陣の演出、声を当てる役者たちの演技。それらが作り上げた「ホウセンカ」の世界観は、アニメ作品が持っていた“新次元の可能性”を大きく広げていく。
異質なアニメらしさが生まれる、抑制と対比の演出論
木下監督はメディアインタビューで、同作について「『ホウセンカ』は今のトレンドからすると少々ニッチな作品かもしれません」と語っている。たしかに「ホウセンカ」の演出は、誤解を恐れずに言えばアニメらしくはない。テンポが良く、動きが派手で、ストーリーの緩急は短い間隔で訪れる…アニメ作品に限らず“現代エンタメ”の多くが取る「一瞬で心を掴む」「飽きさせない」という命題を、至上としなかったのが「ホウセンカ」のもっとも特徴的な点だ。
本作の日常描写は、あたかも昭和時代の人情劇を観ているかのような素朴で静かなリアリティーにあふれている。独房の薄暗さ、会話と会話の「間」、わざとらしさの少ない言葉選び。現代の洗練されたアニメ作品では珍しいほど、一つひとつのシーンを丁寧にゆっくり描いている。
どこかにいる誰でもない男の人生は、ハリウッド作品のような激動に満ちてはいない。人生を振り返るにあたって抑制的なトーンになるのは当然で、だからこそ観客に無意識のリラックスと共感を呼ぶ。余計な動きや音を排除する映像が、結果的により阿久津が人生のなかで抱えてきた“汚れた自分”と“大切な人たち”に対する葛藤や、濃淡さまざまな感情を鮮明に映し出す。
一方で、冒頭から「ろくでもない人生だったな」と辛らつな言葉を突きつけるのが「しゃべるホウセンカ」というファンタジー的存在。それは徹底して抑圧された日常のキャンバスに異質なメリハリを生み出す。限りなく現実に近い世界感と表現であるからこそ、ホウセンカの存在が阿久津の心が生み出した幻覚なのか、それともただのアニメ的表現なのかという“違和感”を観客に植えつける。
物語のなかに出てくるなんでもない会話、ささやかな表情の描写といったものが少しずつ少しずつ興味を惹き、気づけば物語のラストにそれらのピースが一気に繋がるカタルシス。「ホウセンカ」は“昭和人情劇的”であっても、“昭和人情劇アニメ”ではない。アニメだからこその表現と静謐なリアリティーを溶け合わせ、アニメの新しい次元を広げた“踏み込んだ一歩”があるからだ。
(C)此元和津也/ホウセンカ製作委員会
■予告動画
https://youtu.be/g6vg_-XaToE?si=PxANCF6ykY5csot4