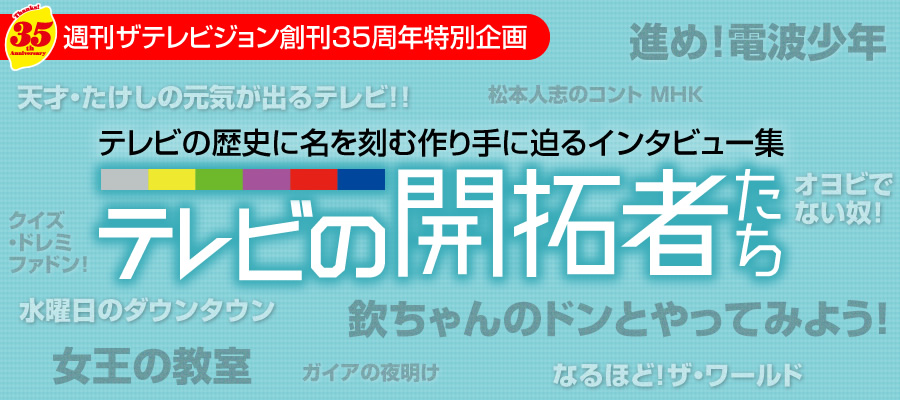「“テレビ屋”の下世話な感覚」を持つクリエイターを育成中【放送作家集団「SACKA(サッカ)」代表・山谷和隆氏】
「マネーの虎」と「松本人志・中居正広vs日本テレビ」は、今でも誇れる仕事です

――では改めて、山谷さんのテレビマンとしてのスタートは?
「大学3年のときにアルバイト情報誌で『テレビ制作』という求人広告を見つけて、一回やってみようかなという軽い気持ちで始めたのが、当時『(天才・たけしの)元気が出るテレビ!!』(1985~1996年日本テレビ系)や、『ねるとん紅鯨団』(1987~1994年)の前身の『上海紅鯨団が行く』(1986~1987年ともにフジテレビ系)を制作していたIVSテレビ制作でした。面接に行ったら、当時IVSの社員だったテリー伊藤さんがいらして、『「元気が出るテレビ」をやってみないか』と声を掛けてくださって。それですぐ『元気が出るテレビ』のADとしてバイトを始めたんです。でも、もういきなり忙しくて。全く家に帰れないんですよ。『このままだと留年で卒業できなくなっちゃうので、大学に戻ります』と伊藤さんに相談したら、『じゃあ、秋の入社試験を受けろ』と。結局、コネ入社みたいな感じでIVSに入社しました」
――初めて携わった番組は覚えていますか?
「ちょうどビートたけしさんがフライデー襲撃事件で謹慎していたころで、その復帰第1弾の『ビートたけしの全日本お笑い研究所』(1988年4~9月、日本テレビ系、6月から『番組の途中ですが…再びたけしです』に改題)という番組でした。半年で終わっちゃいましたけど(笑)、実験的な番組ですごく面白かったんですよ」
――ADの業務は相変わらず大変でしたか?
「そうですね。最初のころは、ロケ先までの移動は全部僕が運転していたので、遠方でのロケがあると大変で。それでも、テレビがかっこいい時代だったので、そういった大変さも、自分は今かっこいいもの、面白いものを作っているんだと思うと、あんまり苦ではなかったですね。
あと、印象に残っているのが、『ねるとん紅鯨団』のADだったころ、ロケのオープニングで、とんねるずの石橋貴明さんから『やまやーっ!』って呼ばれるコントみたいなくだりがあって。それは正直、苦痛でした(笑)。でも今にして思えば、貴明さんからお笑いの指南を受けたというのは、とても貴重な経験ですよね」
――ディレクターとしてのデビューは?
「レギュラー番組では『元気が出るテレビ』ですね。何十本と作っているので、最初に担当した企画は忘れてしまったんですけど、今でもよく覚えているのは、フィンランドのサンタクロース村へ日本の子供を10人くらい連れて行って、本物のサンタクロースに会わせよう、という企画。まずフィンランドへ行くまでに、飛行機で十何時間もかかるので、子供たちのモチベーションを維持させるのが大変で。途中、ドッキリとか用意しても、最初からワンワン泣いてるんですよ(笑)。今では予算的にも、安全性という面でも、なかなかできない企画かもしれませんね」
――その後、フリーディレクターになられてからは、『おしゃれカンケイ』(1994~2005年日本テレビ系)、『メレンゲの気持ち』(1996年~日本テレビ系)、そして『マネーの虎』(2001~2004年)など多数の人気番組を担当されました。
「『マネーの虎』は、撮り方に関してかなり悩みました。いかに視聴者をジリジリさせるかとか、劇画チックな世界をどうテレビサイズに落とし込むかとか、いろんな課題があって。そんな中で意識していたのは、お金を欲しがっている人間のありのままの姿を、視聴者にも分かりやすく伝えたい、ということ。主観・客観のショットを使い分けたり、人物の顔のサイズにもこだわって撮ってました。そうした演出の工夫の積み重ねで、『マネーの虎』のあの独特な世界観を作ることができたのかなと思っています」
――いまだに、バラエティー番組でパロディーにされたりするのも、世界観がしっかり確立されているからなんでしょうね。
「そうかもしれませんね。あと今、フォーマット販売で、世界33カ国で放送されているそうですよ」
――その後、2001年には制作会社のジーヤマを仲間たちと設立されました。
「ジーヤマは、『世界一受けたい授業』(2004年~日本テレビ系)、『フードバトルクラブ』(2001~2002年TBS系)、『ズバリ言うわよ!』(2004~2008年TBS系)などを制作していました。中でも思い出深いのは、『マネーの虎』のスタッフで2回だけやった『松本人志・中居正広vs日本テレビ』(2002年、2003年日本テレビ系)。あの特番は、僕のディレクター人生の中でもドッキリ番組として一番クオリティーが高かったと思います」
――自転車に乗った松本さんをボブ・サップが追いかけて、さらに大玉が転がってきたり(笑)。
「そのコーナーは僕の担当です(笑)。これと『マネーの虎』は、今でも誇れる仕事ですね」