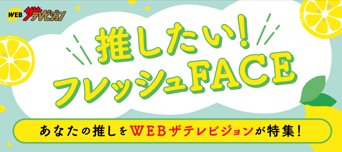2016年、“自身初の社会派作”と銘打ち、20代後半の「ゆとり第一世代」の悩める日常を鮮やかに切り取った連続ドラマ「ゆとりですがなにか」(日本テレビ系)で芸術選奨文部科学大臣賞(放送部門)を受賞した宮藤官九郎。高評価を受け翌年2週連続でスペシャルドラマも作られた同作が、令和になりコロナ禍を経て、6年ぶりに映画「ゆとりですがなにか インターナショナル」(公開中)として帰ってきた。
既に30代半ばにさしかかる正和(岡田将生)、山路(松坂桃李)、まりぶ(柳楽優弥)の3人を取り巻く状況は、この6年で様変わり。新たなZ世代の台頭や、ハラスメント問題、LGBTQへの向き合い、在日外国人の増加など、価値観のめまぐるしい変化にさらされてきた。そんな実社会の世相をまるごと煮込んで提示した宮藤本人は、本作で「社会派コメディーとしての原点に戻った」と述懐する。自ら生み出したヒット作も意外なほど冷静に分析する、当代随一のトップランナーに聞いた。
松坂桃李の一言「~みたいなのできないですかね?」で生まれた劇場版
――今回の映画「ゆとりですがなにか インターナショナル」は、松坂桃李さんからリクエストを受けたことがキッカケだそうですが、キャストの要望を受けて脚本を書くのは、珍しいことですよね?
キャスト発信っていうのは、初めてだと思います。もちろんゼロからじゃなく、既に世界観があるからというのもありますよね。元々、前回スペシャルドラマが終わったあとにも水田(伸生)監督から映画化のお話はあったんですが、僕がなかなか乗らなくて。というのも連続ドラマで始まったものだし、連続ドラマを書く醍醐味がある作品だと感じていたんです。
でも「いだてん~東京オリムピック噺~」(2019年NHK総合ほか)の打ち上げの時に桃李くんが「“ゆとり”のメンバーで『ハングオーバー!消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』(2010年米)みたいなの、できないですかね?」って、それだけ言って帰ったんですよ。
それで「確かにハングオーバーだったら面白いかもな、だったらインターナショナルな設定でまりぶを追ってみんなで上海に行って、酒飲んで分かんなくなっちゃう話を」と水田さんに話して、プロットも書いたんです。それが2020年の2月ごろ。ちょうどダイヤモンド・プリンセス号が横浜沖に到着した頃でした。そしたらコロナがどんどん流行ってきて、海外ロケはダメということになり、でも最近は日本にも外国の方がたくさん住んでるし、そういう話をいろいろ盛り込んで、結局高円寺(正和の元職場だった居酒屋)から八王子(正和の実家)あたりの間でインターナショナル感を出すことになったんです。

――ご自身もコロナに罹患されて。病み上がりで最初に書き上げたのが本作だ、とシナリオ本の「ゆとりですがなにか インターナショナル」の前説にも書かれていますね。
そう、病み上がりで、予定していた劇団の公演も飛んじゃったし、何やっていいか分かんなくて、途中まで書いてたコレを、しょうがない、続き書こうかなって書き始めました。本当は2020年の秋に撮影しようとしていたんですが、それもダメになっちゃいました。
――そこからコロナ禍が3年続いたことでリライトも多々あり、最終的な脱稿まで社会情勢もさらに変化しました。かなり翻弄されたという印象ですか?
それもあるし、時間があったお陰で、本来の「ゆとりですがなにか」にちょっと戻ったような気がしてますね。最初は本当にハングオーバーをやろうとしてて、もっと登場人物が多くて広げた話を想定していたんです。勘が戻ってなかったのかもしれないんですけど(笑) 、正和の会社を買収した韓国企業の上司チェ・シネ(木南晴夏)の話は、もっと重たかったし。でも延期になって水田さんとやりとりしていくなかで、もう少し話を絞り込む方向で改訂して、この形になったんですよね。
前はゆとり世代が社会問題そのものだったんだけれど、今回は、ゆとり世代はもう社会の真ん中にいて、他の問題――男女同権とか、LGBTQとか、格差とか――を目の当たりにするという形に、最終的になっていきました。
そういう社会情勢も、今のエンターテインメントでは触れないでおくのが安全じゃないですか。でも触れないと「これがいい/これが悪い」っていうことすら言えない。例えばハラスメントはいけない、ということを言うためには、ハラスメントの場面を描かなくちゃいけない。でもそれだけで「けしからん」って目で見られる…まぁ、そもそも僕はそういう目で見られがちなんですが。しかも、コメディーにしないとやる意味がないんで、そのさじ加減がすごく難しかったですね。でも2016年に連続ドラマをやった時も「コメディーだけど社会派だ」っていうことは常に頭の中にあったので、そこに戻ったのかなっていう気はしますね。

バップ