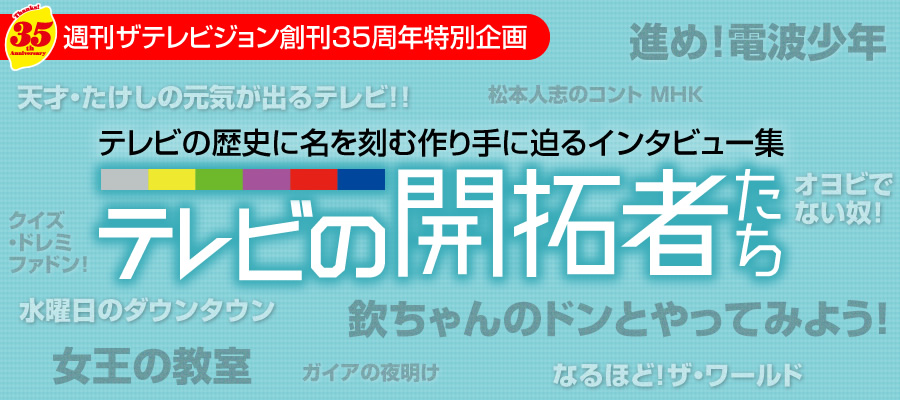【テレビの開拓者たち / 菅賢治】「これからは作り手の手腕が試される時代」
番組制作会社勤務を経て、1988年に日本テレビに入社。「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」(1989年~)や「踊る!さんま御殿!!」(1997年~)など、日本テレビの人気バラエティーを数多く手掛けてきた菅賢治氏。2014年に独立後も、中京テレビで放送中のトーク番組「太田上田」の企画・プロデュースをはじめ、“面白い番組作り”に情熱を注ぎ続ける彼に、作り手としての信条や、恩人・明石家さんまとのエピソード、さらに、昨今のテレビに対する思い、自身の今後の夢についても語ってもらった。
バラエティーとは本来ウソをつくもの。だからこそ入口は“リアル”でなければダメなんです

──菅さんがバラエティー番組を作る上で、最も大事にされていることは何でしょうか?
「何よりも“リアル”でなければダメだと思っています。バラエティーというのは、本来ウソをつくものなんですけど、まず入口はリアルにしておかないと。その上で、そこから先をウソで盛っていくから面白くなる。ウソから始めてしまうと、その後のウソがつけなくなりますから。
『恋のから騒ぎ』(1994~2011年日本テレビ系)でも、出演者の女の子たちに常に言っていたのは、『何をしゃべってもいいけど、ウソだけはつかないでね』と。彼女たちのリアルなエピソードに対して、(明石家)さんまさんがツッコミを入れるのが『から騒ぎ』の面白さなわけで、そこがウソになってしまうと、番組がめちゃくちゃになってしまう。それ以前に、ウソのトークは、絶対さんまさんに見破られちゃうんですけどね(笑)」
──そういった信条は、いろいろな番組を作られていく中で、徐々に培われていったものなのでしょうか?
「僕は日本テレビに中途入社する前、7年くらい制作会社にいたんですが、『酒井広のうわさのスタジオ』(1982~1987年日本テレビ系)というワイドショー番組のディイレクターをやっていた時期があって。テレビはリアルでなければいけない、というのは、その番組で教わった気がします。
テレビを批判する言い方のひとつに、“やらせ”っていうのがありますよね。でも、昔は“やらせ”は決して悪い意味で使う言葉じゃなかった。例えば、甲子園出場が決まった高校球児が『オー!』とか言いながら、みんなで拳を突き上げたりするじゃないですか。ああいう風に、リアルな状況の中で何かをやってもらうことを“やらせ”と言っていたんですよね。今では、“やらせ=ねつ造”という意味合いになってしまったので、僕らも使えない言葉になっちゃいましたけど」
――さまざまなバラエティー番組を手掛けている菅さんですが、われわれテレビ好きにとっては、中でも明石家さんまさん、ダウンタウンの番組のプロデューサー、という印象が強いんですけれども。
「確かに、さんまさん、ダウンタウンさん、この2組と仕事をしていなかったら、間違いなく今の僕はないですね。
さんまさんには、『さんま・一機のイッチョカミでやんす』(1989~1990年日本テレビ系)で僕がディレクターをしていたころ、バラエティーの作り方を一から教えてもらいました。『イッチョカミでやんす』は、さんまさん、小堺一機さんたちによるスタジオトークがあって、そのトークで出てきた話題をコントにして披露する、という構成だったんですが、そのころの日本テレビには、僕も含めてコントの作り方を知っているスタッフが誰もいなかったんですよ。だから毎週コントを収録した後、スタッフ全員でプレビューしながら、さんまさんからアドバイスをもらっていました。『こういうときはこういう風に撮って』と、それはもう一から教えてもらいましたね。さんまさんは『君ら、ホンマに何にも知らんのやな』なんて、あきれて笑ってましたけど(笑)」