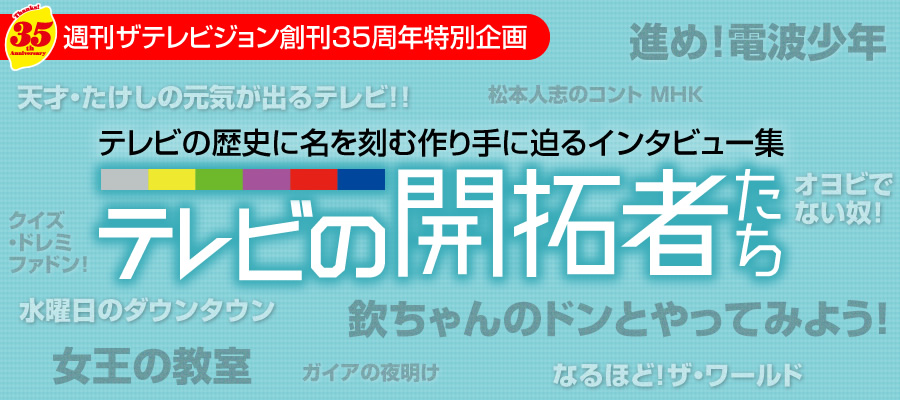【テレビの開拓者たち / 堤幸彦】「墓場に持っていく作品のテーマ探しに入っています」
テレビでは表現してこなかった領域に踏み込みたいと思って作ったのが「ケイゾク」でした

──ところで、堤監督作品といえば、“堤幸彦”という名前を世に知らしめたのは「金田一少年の事件簿」をはじめとする、数々の日本テレビ系のドラマでしたね。
「僕はそれ以前にも映画やドラマを撮っていて、当時の日本映画の作り方に不自由さを感じる一方、まんじゅう工場みたいに判で押したような連ドラを量産する体制にも違和感があって。映画はもっとカジュアルに撮れないか、ドラマはもっと映画っぽく作れないか、そんなことを考えていたんですね。その実験の一発目が『金田一少年の事件簿』だったんです」
――具体的に、どのような「実験」を?
「池田屋という自分の分身のような会社(※映像技術プロダクション)で丸ごと引き受けて、予算の枠をキープしつつ、とんがったものを作ろうっていう。そして、その成果を持って、従来のテレビでは表現してこなかった領域にさらに踏み込みたい、と思って作ったのが『ケイゾク』でした。実際、クリエイティブ面では振り切ったという達成感はありましたね。そう考えると、『金田一少年』のプロデューサーの櫨山裕子さんや、TBSの植田さんは恩人であり、同志。もちろん、その後の『池袋ウエストゲートパーク』(2000年TBS系)の磯山晶プロデューサーや、『TRICK』(2000年ほかテレビ朝日系)の桑田潔さん、蒔田光治さん、山内章弘さんといったプロデューサーの方々も同じで、いずれも理想に近い形で作品作りに臨むことができました」
──そんな経歴から言っても、堤監督はまさに「テレビの開拓者たち」という本特集にふさわしいクリエイターだと思います。
「いやいや。ザテレビジョンさんには、ありがたいことにドラマアカデミー賞のトロフィーをたくさんいただいたりもしてますけど(笑)、僕なんか全然。本当に開拓者と呼ばれるべきは、先人の方々でしょう。例えば、久世光彦さん。これはあちこちで話してますけど、久世さんは僕にとっての神なんですよ。『寺内貫太郎一家』(1974年TBS系)とか、『ムー』(1977年TBS系)とか、久世さんの演出した一連の作品を見ていなかったら、僕はこの仕事をしてないですから。よく僕のカメラワークが新しいなんて言っていただけますけど、久世さんはそんなもんじゃないですよ。あの窮屈なスタジオカメラで、ものすごい引きの画からどアップの画まで、カメラを割らずにズームアップで撮ったりしますからね。 あとは、樹木希林さんが『ジュリー!』と叫ぶ、ドラマという虚構の世界にジュリー(沢田研二)というリアルなものが入ってくる面白さですよね。本当に衝撃的で、僕も『ケイゾク』で、事件現場にある特定のジーンズショップの袋が血まみれになって落ちているというような、リアルな記号を使った表現を始めました。一方で、久世演出作品には、向田邦子シリーズのような、東京の下町を舞台にした心温まる作品もある。僕も今後は積極的にそういうアプローチもしてみたいと考えています」